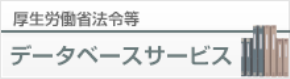豊橋労働基準協会や愛知労働局からの『お知らせ』

熱中症を防ごう!!
事業者が取組むべき事項
1.WBGT値の把握と評価 2.WBGT値の低減等
3.作業時間の短縮・休憩 4.休憩場所の整備等
5.暑熱順化 6.水分及び塩分摂取のための整備
7.服装等 8.健康診断結果に基づく対応等
9.労働衛生教育 10.作業場の管理
作業者が取組むべき事項
1.日々の健康管理 2.適切な休憩
3.水分及び塩分の接種 4.異常を感じたらすぐに申し出る
※詳しくは、左のリーフレットをクリックしてください。

(県下労働基準協会が行う)
無料相談「企業の労働110番」のご案内
~ (052)961-7110 までお電話を ~
愛知県下の労働基準協会では、様々な労働問題の解決の一助となるべく、名北労働基準協会の協力を得て労働相談室を設けております。
企業から寄せられる、法律内容のご質問、行政への手続方法、就業規則作成・改訂、労使紛争解決などの様々な相談活動を無料で実施します。 お電話、メール、ファックス、ご来局でのご相談に、企業の立場にたったアドバイスを、労働の専門家が問題解決まで何度でも行います。
相談専用ダイヤル 企業の労働110番 052-961-7110(企業の労働 何でも110番)
労働相談は、秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策をアドバイスします。労働者の立場からのご相談には応じません。
愛知県下の労働基準協会の会員企業様は、解決まで何度でもご相談ください。労働基準協会に未入会の企業様は、初回協会にご来局いただいた場合に限り無料でご相談に応じます。
【企業の労働110番労働相談室】
・対応者:社会保険労務士等(月~金8:30~17:30
祝日等は除く)
・運営(場所):(一社)名北労働基準協会 1階相談室
(名古屋市北区清水1-13-1)
・来局の場合:お電話にてご予約ください。

愛知働き方改革支援センターからのお知らせ
相談無料:こんなお悩みありませんか
・就業規則見直し
・賃金引上げに向けた取組み
・活用可能な助成金
・三六協定の締結・届出
・同一労働同一賃金・人材不足対応(育成含む)
・人材不足対応(育成含む)
・業務効率化から始めたい
・時間外堂々の上限規制
★ 東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況はこちら
● 技能講習や特別教育を受講される皆様へ【本人確認のお願い】
公益社団法人愛知労働基準協会主催の技能講習や特別教育などを受講される皆様へのお知らせです。
愛知労働基準協会主催の技能講習や特別教育などを受講される場合は、自動車運転免許証やパスポートなど公的機関が発行する顔写真付きの受講者本人が確認できるものが必要となりました。
受講者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、講習会全日にわたって、本人確認のできるものをご持参いただきますようご協力をお願いします。


豊橋市が
「とよはし産業人材育成センター」
を開設
旧港湾技能研修センター(豊橋市神野新田町)は、神戸市に機能移転したことにより令和2年3月に閉鎖されましたが、この施設を産業振興及び人材育成等のために活用してほしいとの意向により、一般財団法人港湾労働安定協会から豊橋市に寄贈されました。これにより、地域の産業人材育成を担う拠点の一つとして、令和4年4月から「とよはし産業人材育成センター」が開設されました。
同センターでは、会議室や教室等の貸し出しを行っており、事業所内の研修や会議等での利用が可能となっています。
今後、豊橋市は教習用のフォークリフトなどの導入を予定しており、協会としては、同センターで
様々な講習を実施していく方向で計画をしています。
案内図(駐車場)の詳細は、上記の画像をクリックしてください。
シーパレスリゾートから入ることは出来ません。
お問い合わせ先:豊橋市役所 産業部 商工業振興課 ☎ 0532-51-2437
とよはし産業人材育成センター ☎ 0532ー31-0151


~~ 愛 知 労 働 局 か ら の お 知 ら せ ~~

愛知労働局における令和6年度の行政運営方針が
示されました
(多義に渡るため目次は一部の項目をご紹介してあります)
※左記、行政運営方針をクリックすると
内容をご覧になれます
目 次
第1章 愛知の労働行政を取巻く情勢
1労働行政を取巻く現状と課題
2多様な人材の活躍をめぐる現状と課題
3安全で健康に働くことができる環境づくりをめぐる現状と課題
第2章 最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善
1最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援
2非正規雇用労働者の正規化促進、雇用形態に関わらない公平な待遇の確保
第3章 リスキリング、労働移動の円滑化等の推進
1リスキリングによる能力向上支援
2成長分野への労働移動の円滑化
3中小企業等に対する人材確保の支援
第4章 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり・就職支援
1女性活躍のための支援及び多様な働き方、働き方・休み方改革
2ハラスメント防止対策
3安全で健康に働くことができづ環境づくり
4仕事と育児・介護の両立支援
以下省略
愛知労働行政のあらまし~Profile2024~ 👈 はココをクリック

(厚生労働省作成の詳細は👆ここをクリック)
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
厚生労働省は、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた、令和5年4月から令和10年3月までの5年間を計画期間とする「第
14 次労働災害防止計画」を策定しました。
厚生労働省の計画策定を受け、愛知労働局は県内の労働災害防止を推進するための取組む事項を定めた、中期計画「第 14 次労働災害防止推進計画」を公表しました。
愛知労働局作成「第 14 次労働災害防は上記の画像をクリックしてください
愛知労働局 雇用環境・均等部
(国が行う) 個別労働紛争解決制度のご案内
~ 簡易・迅速・無料・秘密厳守 ~
職場のトラブル解決をサポートします。(詳細は、愛知労働局ホームページ👈ここをクリックして下さい。)
職場でのトラブル解決をサポートする制度として「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度があります。
1 労働相談 2 助言・指導 3 あっせん
*上記制度は労働者、事業主どちらからでも利用可能であり、無料です。
問い合わせ、お申し込みは総合労働相談コーナー(県下15か所・豊橋労働基準監督署内☎0532-81-0390)にお願いします。(詳細は、厚生労働省ホームページ👈ここをクリックして下さい。)
■ 2019(平成31)年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)≪働き方改革関連法≫は、平成30年4月6日に第196回国会に法律案が提出され、同国会において、一部修正の上、6月29日に可決成立し、7月6日に公布されています。
働き方改革を実現するためには、すべての企業にしっかりと取り組んでいただくことが必要ですが、とりわけ、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者に働き方改革の趣旨をご理解いただくことが重要と考えています。
当協会に対しても、平成30年7月27日付けで愛知労働局長から、成立、公布された同法律の周知要請がありましたので、お知らせします。
ポイント1
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019(平成31)年(中小企業2020(令和2)年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019(平成31)年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020(令和2)年(中小企業2021(令和3)年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
※ 詳細は、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。(こちらをクリック)
【時間外労働の上限規制など改正内容を説明した各種リーフレット、36協定届の記載例などもご覧になれます】
● 愛知労働局のホームページにも掲載されています(こちらから)
---------------------------------------------------
■ 令和2年4月1日から「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)」が施行されます
改正労働者派遣法の改正点は、
1 不合理な待遇差別をなくすための規定の整備
2 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備、となっています。
---------------------------------------------------
■ 愛知の「働き方改革」

~ 「働き方改革」でワーク・ライフ・バランスの実現を進めましょう ~
愛知労働局は、「働き方改革」推進本部を設置し、「働き方改革」の実現に向けて、地域の経済団体・労働団体のトップへの働きかけや、気運の醸成を図るなどの取組を行っています。
【画像をクリックすると愛知労働局ホームページへ】
---------------------------------------------------

○ 愛知働き方改革推進支援センターをお気軽にご活用ください!
~「働き方改革」に取組む皆様を応援します~
・ 人手不足を解消したいけど、何をすればいいか分からない
・ 賃金を引き上げるため、会社の生産性を向上させたい
・ 助成金を利用したいけど、うちが活用できる制度を教えてほしい
・ 従業員の能力向上を図るための効果的な育成制度を導入したい
・ IT化を進めたいけど、対応できる従業員がいない
このようなお悩みの事業主様はいらっしゃいませんか?
電話:0120-006-802
画像をクリックしてください。👆
愛知労働局のホームページに繋がります
■ 「論理的な安全衛生管理」の推進・定着

愛知労働局では、安全衛生を科学的、論理的に考えていただくため、
「論理的安全衛生管理の推進・定着」の特集コーナーを設けています。
安全衛生を基礎から考えてみましょう。
【画像をクリックすると愛知労働局ホームページの特集コーナーへ】
■ 「治療と職業生活の両立支援」について
~あんしん(安心)して、いきいき(活き活き)と、ちりょう(治療)しながら、働ける職場環境づくりを目指して!!~
「治療と仕事の両立支援」は、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取組です。
政府は、「働き方改革実行計画」(平成29年3月働き方改革実現会議決定)に基づき、治療をしながら仕事をしている方の治療と仕事の両立に向けた様々な取組を推進することとしています。
愛知労働局では、県内の両立支援に取り組む民間団体や自治体等の関係者が密接に連携を図り、各企業で、団体・関係者が提供する各種支援サービスや、産業保健総合支援センター、労災病院が実施する支援サービス等の利用促進が図られるよう、「あいち地域両立支援推進チーム」を設置して環境整備に努めています。これらの支援サービスを積極的に活用いただき、治療と仕事の両立に取り組まれるようお願いします。
● 厚生労働省は、平成28年2月に、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を策定しています。
このガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。
ガイドライン、参考資料はこちら(厚生労働省のホームページへ)
---------------------------------------------------

● こんな人は、まわりにいませんか?
・ がんと診断されたけど仕事を続いけたい
・ 病気のことを会社にうまく伝えられない
・ 治療と仕事を両立できるか不安
・ 今後の働き方について誰に相談したらいいか分からない
・ 職場の理解、協力が得られない
・ 治療に合わせた短時間勤務や、休暇の取得が難しい
治療と職業生活の両立で悩んだら、産業保健総合支援センターの「両立支援促進員」までご相談ください。
愛知産業保健総合支援センター(名古屋市中区新栄町2-13、栄第一生命ビル9F)
画像をクリックしてください(令和2年2月7日掲載)

■ 職場の「受動喫煙防止対策」は事業者の努力義務です
健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図ることの重要性が増しています。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課しています。
令和2年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。
画像をクリックしてください
■ 女性活躍推進法等の一部を改正する法律(ハラスメント対策強化を含む)が成立
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
○ 改正女性活躍推進法等の施行期日
・ 改正女性活躍推進法のうち、
行動計画策定・情報公開義務の対象拡大:令和4年4月1日
情報公開の強化・勧告違反の公表等 :令和2年6月1日
・ 改正労働施策総合推進法
パワーハラスメント防止のための事業主による雇用管理上の措置義務の新設等:令和2年6月1日(中小企業は4年3月31日までは努力義務)
・ 改正男女雇用機会均等法
事業主への相談等を理由とした不利益取扱の禁止、調停の意見聴取の対象拡大等:令和2年6月1日
・ 改正育児・介護休業法
事業主への相談等を理由とした不利益取扱の禁止等:令和2年6月1日
○ 育児・介護休業法施行規則等の改正
・ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります : 令和3年1月1日から
※ 職場におけるハラスメントの防止に関する厚生労働省のホームページはこちらをクリック


◆◆ 労働基準行政関連施策等の紹介 ◆◆
【厚生労働省ホームページ掲載の関連バナーなどを抜粋】

画像をクリックすると、厚生労働省のホームページにリンクします。
厚生労働省では、外国人労働者の安全衛生対策に活用いただける教材を提供しています。
安全衛生教育、建設業(教材)、農業(教材)、漁業(教材)、
造船・舶用工業(教材)、建設就労者・造船就労者向け(教材)、技能講習補助教材
■ 厚生労働省「働き方改革実現に向けて」

★「働き方改革関連法」が成立し、改正労働基準法などが平成31年4月1日から順次施行されています
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が平成30年7月6日に公布されました。平成31年4月1日から順次施行されています。
画像をクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ
法律の概要や法律条文、解説リーフレットなどは上の画像をクリックし、厚生労働省のホームページからご覧ください。
■ 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」

厚生労働省では、社員の働き方・休み方の見直しや、改善に役立つ情報を提供する目的でポータルサイトを開設しています。
このサイトでは、働き方、休み方改革を進めるための支援策や、シンポジウム・セミナー(無料)の開催情報が掲載されています。働き方・休み方の改善にご活用ください。 バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」へ
■ 厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(令和2年3月18日更新)

厚生労働省は「トラック運転者の地用時間労働改善に向けたポータルサイト」を令和元年9月6日に開設しました。
トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。
ポータルサイトでは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取組施策などを一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ
■ 厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」(令和2年1月14日開設)

テレワークに関する様々な情報を得るための入口となるWEBサイトです。
「言葉は聞いたことがあるが、よく分からない」、「どんなメリットがあるのか分からない」、「テレワークを導入したいが、手順が分からない」、「テレワークは今どのような状況なのか調べたい」など、このサイトを活用し、テレワークの導入、知識の拡大、事例研究、助成金の活用を進めてください。
画像をクリック ⇒ 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」へ
■ 厚生労働省「「過労死ゼロ」を実現するために
~ 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ ~

「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死とその防止に対する理解を深めて「過労死ゼロ」の社会を実現しましょう。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ
■ 厚生労働省「確かめよう労働条件」

アプリで労働条件に関する法律をクイズやマンガを通じて学習できる!
アプリで確かめよう・WEBで確かめよう
働く時のQ&A、学習コンテンツ、相談機関、アルバイトの条件など
画像をクリック ⇒ 厚生労働省「労働条件に関する総合情報サイト」へ
---------------------------------------------------
★ 知って役立つ労働法 ~働くときに必要な基礎知識~
厚生労働省は、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック『知って役立つ労働法 ~働くときに必要な基礎知識』を作成しました。
労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、労働法を分かりやすく解説しています。ご活用ください。
■ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」

厚生労働省では、新規起業事業場などが労務管理や安全衛生などについて、ウェブ上で診断を受けられるポータルサイト「スタートアップ労働条件」を開設しています。
このサイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」「就業規則、賃金、労働条件、年次有給休暇」「母性保護、育児、介護」「解雇、退職」「安全衛生管理」「労働保険、社会保険、その他」の6項目について、設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができます。また、診断の結果、問題点が認められた場合には改善に向けた情報を提供します。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」ポータルサイトへ
■ 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
■ 厚生労働省「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」
~ メンタルヘルスに関する情報 ~

厚生労働省では、事業者、産業保健スタッフ、労働者などの方々に対して、メンタルヘルス対策の基礎知識、事業場の取組事例、各種研修の案内、各種リーフレット等の総合的な情報提供等を行うため、特設サイトを開設しています。
職場のメンタルヘルス対策にご活用ください。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「こころの耳」特設サイトへ
■ 厚生労働省「あかるい職場応援団」
~ 職場のパワーハラスメントを予防しましょう ~

厚生労働省では、「職場のパワーハラスメント」を予防するするための取組に向けての特設サイトを開設しています。
各種情報、社内研修用資料などが掲載されていますので、ご活用ください。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「あかるい職場応援団」の特設サイトへ
---------------------------------------------------
● 職場におけるハラスメント関係指針(令和2年1月15日厚生労働省告示5号)
~職場におけるパワーハラスメント対策が令和2年6月1日から大企業の義務になります (中小企業は令和4年4月から)~
セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関する対策とともに対応をお願いします。